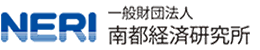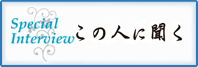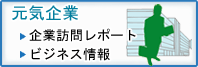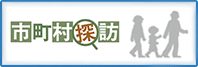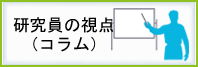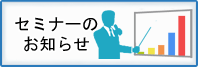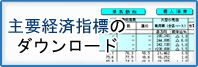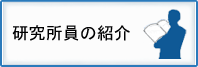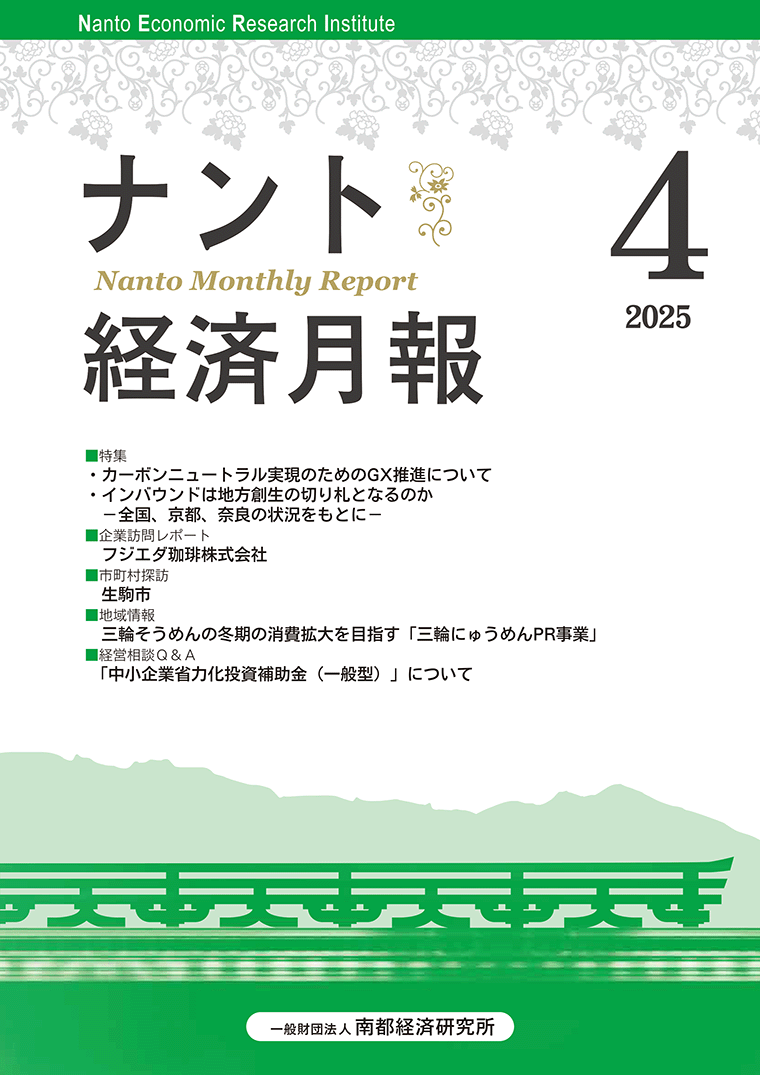| 県内地元産業の現況 | |
近畿経済産業局発表の「百貨店・スーパー販売 状況」によると9月の奈良県の百貨店・スーパー販売額(全店ベース、速報)は、前年同月比0.8%減少(近畿合計:2.9%増)と前年を下回った。
商品別内訳をみると、飲食料品は前年と比較して0.4%増加(同2.3%増)、衣料品が14.9%減少(同0.4%増)、身の回り品が11.1%減少(同0.5%増)。
4月から始まった大阪・関西万博は、当初の予想を上回り、一般来場者数が2,500万人以上となるなど大盛況の中184日間の会期を終えた。国内だけでなく海外からも多くの人が訪れ、特に開催地大阪周辺は、百貨店やスーパーの売上が好調となった。
9月、10月の県内百貨店・スーパーにおける状況は、物価高騰が進む中10月から食品や飲料の値上げが半年ぶりに3,000品目を超え、これまで以上に家計負担は重くなっている。
昨年は「令和の米騒動」と呼ばれるほど米不足と価格の高騰が話題になったが、今年は価格高騰が続いているものの、店舗には多くの米が並んでいる。ある店舗では「新米の収穫量が増えているため今後価格は下がっていくだろう」と話す。
その他の飲食料品の物価高も続いているため、消費者の節約志向は引き続き高い。「商品単価が高いため、買い上げ点数が減っても売り上げを維持している。ただ店舗利用者数は減少しており、買い控えの傾向は以前より強まっている」との声も聞かれる。
衣料品は、長引く残暑の影響で秋物の販売が振るわなかった。「消費者は、気温や気候など季節を感じることで衣料品の購入を考える。最近は四季を感じられなくなり、市場も年々小さくなってきたように感じる。セールなどをしても以前に比べて盛り上がりに欠ける」との声もあり、依然厳しい状況となっている。
観光庁「宿泊旅行統計調査」によると、県内宿泊施設における夏季(6月~8月)の稼働率は各月で前年を上回り、宿泊者数も各月で前年から増加した。大阪・関西万博の開催期間中は、会場となった大阪府に観光客が集中し周辺の都道府県では宿泊客数が減少する月もあったが、奈良県はコロナ禍以降に開業した新しい施設が総じて好調に推移したことに加え、外国人の宿泊者数が大幅に増加したことで、各月とも前年比プラスとなった。大阪市、京都市の宿泊料が高騰し相対的に宿泊料が割安な奈良県に宿泊客が流れたこと、また日本人観光客において大都市の混雑を避け静かな環境で宿泊する動きがあることなども背景にあるようだ。
秋の行楽シーズンは、寺社巡りや正倉院展などの文化観光に伴う宿泊需要が好調で、日本人、外国人ともに好調に推移している。このシーズンのリピーターに多い関東方面からのシニア層については、宿泊施設でゆっくりと滞在を楽しむ傾向が近年顕著になっている。
修学旅行は、概ね例年通りの受け入れ状況となっている。一方で、首都圏から関西方面への旅行費用がかさみ、首都圏の学校では旅行費用の安い北陸などに行き先を変更する動きが出てきた。これに少子化による生徒数の減少も加わり、県内での宿泊を伴う修学旅行の減少を懸念する声がある。
2026年は、同年放映のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で大和郡山市が舞台の一つとなるほか、「飛鳥・藤原の宮都」のユネスコ世界遺産登録への期待もあり、全国から奈良県に注目が集まる。現在奈良市内に集中している宿泊客が県内を周遊するきっかけになり、ひいては奈良市以外の観光地の魅力をPRする機会になると考えられる。各地域においては、旅行者の満足度を向上させ、リピーターを増やす取り組みが重要となる。
国土交通省「住宅着工統計」によると、2025年4月~9月の木造住宅の新設着工戸数は前年同期比13.6%減少。建築基準法改正(2025年4月)による設計士等の費用増加や工期の長期化を見越した駆け込み需要の反動により、大幅な減少に繋がったものと見られる。
(一財)日本木材総合情報センター「10月の木材価格・受給動向」によると、梁(はり)や柱に用いられる構造用集成材の原料となる欧州産ラミナ(集成材を構成する挽き板あるいは小角材のピース)は、円安が進行し仕入れ価格が上昇している。
一方、木造住宅の着工件数は減少し、住宅市況の低迷下での製品価格の値上げは困難な状況にある。加えて人件費の上昇や燃料費の高止まりが続いているため、製材業者にとっては厳しい経営環境が続いている。
今後も少子高齢化や若年層の木造住宅離れにより国内市場の縮小が長期的に予測されることから、業界では、中高層建築物や非住宅分野への木材利用拡大や、ZEH※対応住宅への取組みが進められている。
※ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
断熱・省エネ性能を高めて消費量を減らしつつ、再生可能エネルギーを生み出し、それらを合わせることで消費量が実質ゼロ以下になる住宅を指し、日本を含め世界各国で普及を進めている。
経済産業省「生産動態統計」によると、2025年7~9月期の靴下(パンスト除く)生産数量は8,995千点と前年同期比23.0%減少し、パンスト生産数量も8,127千点と同29.5%減少した。
都心部の一部ではインバウンド需要が見られるものの、物価上昇による節約志向の強まりから販売環境は厳しく、生産数量は減少していると考えられる。
製品別でみると、靴下(パンスト除く)では、7月に中規模事業者が倒産したことに続き、10月にも倒産が発生するなど、県内でOEM生産を主力とする事業者が相次いで撤退したことにより、生産数量の縮小を招いた。
パンストについては、2023~2024年にかけて県外の中規模メーカーが相次いで倒産したほか、今年3月には県外の大手メーカーが生産工場を閉鎖するなどの影響で、生産数量は減少した。
薄利多売型のOEM生産では、販売店が求めるロット数が縮小し、従来の多売モデルが成立しにくくなっていることから、OEM生産への依存度が高い事業者ほど、先行きの厳しさが増している。
こうした状況下、各社は自社ブランドの強化や小売店との直接取引の拡大など、独自戦略で活路を見出そうとしているが、OEM生産の縮小が続く中では、生産数量減少に歯止めがかかる見通しは立っていない。
国土交通省の建築着工統計調査による2024年10月から2025年9月までの1年間の県内の工事費予定額は2,203億円で、民間工事は前年比7.5%減少、公共工事は同41.6%増加となった。
なお、民間の建築物の棟数は前年比4.9%減少、床面積も同7.7%減少となった。
上記調査のとおり、民間工事は資材コストや労務コストの上昇に伴い建築費が高騰し、工事の中止や延期または規模の縮小により、当面は低調な状況が続くものと思われる。
一方、公共工事は国土交通省による京奈和自動車道未開通部分の工事が進められている他、奈良県では、中央卸売市場再整備計画や水道管改修事業が控えており、今後もインフラ更新を中心に高水準で推移することが予想される。
多くの建設業者は、専門技術者をはじめ、建設作業員から現場監督者まで高齢化や人手不足等の課題を抱えており、円滑に公共工事等を請け負い、持続的に発展するためには、官民挙げてこの問題に取り組む必要がある。
こうしたなか、奈良県建設業協会が主催し奈良県が後援する合同企業説明会を今年も実施するなど、地道な活動が続けられている。また、地場の大手・中堅企業の中には、スーパーゼネコンの退職者、外国人や女性を積極的に採用する動きも見られる。
内閣府「機械受注統計」によると、全国の2025年9月の機械受注は、工作機械が前年同月比5.6%増で3か月連続の増加。電子・通信機械は同9.5%増で2か月連続の増加。産業機械は同3.5%減で2か月連続の減少となった。
「奈良県鉱工業指数(2015年=100:注)」で奈良県の2025年4月~2025年9月の機械の生産指数(原指数・平均)をみると、一般機械工業は前年同期比7.0%減の63.6、電気機械工業は同49.5%増の16.3、輸送機械工業は同0.7%増の68.5だった。
*注:抽出調査のため生産量全体の増減を示すものではない。
奈良県内の企業の動きをみると、中国のEV自動車市場の失速により設備投資の先送りなど一部で弱い動きがみられるものの、生成AI向けの半導体製造装置や電子部品関連などの需要は堅調で、受注・生産は総じて底堅く推移している。
原材料価格は落ち着いているが、電気料金、運送費、人件費等の上昇が続いており、価格転嫁交渉において、競合先が多い海外メーカーなどの取引先から理解を得ることに苦慮している。
米国の関税政策による影響が顕在化する兆しもあり、海外経済の減速懸念から先行きに対する不透明感が強まっている。安定的な業績確保のため、研究開発投資の促進など自社の技術力を高めることで、新市場の開拓や新規事業への参入に取り組む動きがみられる。